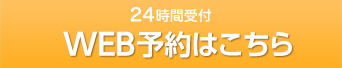精神医学における医療情報発信に関し、倫理規定を解説
精神医学分野における医療情報の発信は、患者のプライバシーや尊厳を守りつつ、
正確かつ適切な形で情報を提供する必要があります。とりわけ精神医学は、社会的な偏見や
誤解を受けやすい分野であるため、医療者は高度な倫理的配慮をもって情報を発信しなければなりません。
以下では、日本国内で一般に参照される倫理規定や指針、およびそれらが医療情報発信に
どのように関係しているかを解説します。
まとめ
・科学的に正しい情報であるのか? 個人的見解の場合、それがわかるように区別されているか?
・専門家として、パラソーシャルな主体としての影響力を配慮しているか?
・個人情報は守られているか? 守秘義務を犯していないか?
・ゴールドウォータールールに反していないか?
・インパクトと意図 内容が刺激的すぎないか? 正しい意図のもとに情報発信されているか?
・害を与えるものでないか? 差別的ではないか?
・刑法や民法に該当するような、名誉毀損などの問題はないか?
・医療広告法は犯していないか?
(おまけ:情報発信者の心的疲労について)
1. 医療倫理の基本原則
1-1. 自律尊重の原則(Respect for Autonomy)
- 患者の自己決定権を尊重することが基本です。
- 情報発信の場面では、患者や一般市民にとって「分かりやすく」「正確で適切」な情報を
示すことで、自分自身の意思決定に役立ててもらうことが重要となります。 - 一方で、受け手が誤解を招くような表現や、データを一部抜き出して過度に誇張するなどの行為は
患者の自己決定を妨げる可能性があり、倫理的に問題となります。
1-2. 善行の原則(Beneficence)と無害の原則(Non-Maleficence)
- 可能な限り患者や社会にとって有益な情報を提供し、害が及ばないように配慮することが求められます。
- 精神医学の分野では、誤った情報や断片的な情報を発信すると、患者やその家族、一般の方々の
不安や偏見を助長するリスクがあります。 - 特定の治療法に対して過度な期待を煽る、あるいは逆に恐怖を与えるような発信は避けるべきです。
1-3. 正義の原則(Justice)
- 情報へのアクセスが公平になるよう配慮し、不必要に特定の治療やサービスに誘導したり、
一部の層を排除したりしないことが求められます。 - 広告や商業的な利益を優先しすぎるあまり、公平性を欠く情報発信がないように注意が必要です。
2. 日本精神神経学会等による倫理指針
2-1. 日本精神神経学会 倫理指針
日本精神神経学会では、精神科医療における倫理的態度や守るべき基本姿勢などを示す
「倫理指針」や「ガイドライン」を発表しています。例えば、
- 患者のプライバシー保護
- 診療上の守秘義務の遵守
- 科学的根拠に基づいた情報提供
- 不当な差別や偏見を助長しない表現の遵守
などが明文化されています。これらの指針は学会員に限らず、
精神医学・医療従事者が遵守すべきスタンダードと考えられています。
2-2. 情報発信に関する指針のポイント
- 専門家としての責任:
医療情報を公に発信する際、専門家としての立場からの情報であることを自覚し、
その信頼性と根拠を明示する。 - 患者のプライバシー保護:
症例紹介などを行う場合でも、個人が特定されないように細心の注意を払う。 - 差別的表現の排除:
「精神疾患=危険」という誤解を招くような表現や、レッテル貼りを避け、
偏見を助長しない言葉選びに配慮する。 - 営利目的の過度な強調の排除:
治療法や薬剤について、営利目的で過度に強調しない。利益相反がある場合には必ず開示する。
3. 守秘義務・個人情報保護との関係
3-1. 個人情報保護法等の遵守
- 日本の法律では、個人情報保護法をはじめ、患者情報の取り扱いについて厳格な規定があります。
- 精神医療では、患者情報がデリケートであることから、匿名化やプライバシー保護には特に配慮しなければなりません。
- 講演会や学会発表、SNSでの情報発信の際にも、実名や顔写真、詳細な家族構成等が推測できる形での情報公開は厳禁です。
3-2. 守秘義務
- 医師法第24条や倫理綱領により、医師は業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
- 患者の事例を挙げる場合でも、診察時のエピソードなど、第三者から見て特定できる可能性があれば
守秘義務違反に抵触する危険があります。 - 精神科領域では、患者個人に関わる情報が社会生活に大きな影響を及ぼしかねないため、
徹底した厳守が必要です。
4. メディアやSNSでの情報発信における留意点
4-1. SNS・インターネット上での情報発信
- 誰もが手軽に情報を発信できる時代だからこそ、専門家による正確な情報発信が求められます。
- 一方で、受け手のリテラシーはさまざまであり、文脈が省略されがちなSNSでは誤解を招きやすいという問題があります。
- 短い文章や刺激的な言葉が注目されやすい特性を理解したうえで、正確性を担保しつつ感情的・煽情的な言葉は避けることが推奨されます。
- インパクトだけで判断するとどうしてもセンシティブな話題は扱いにくいです。道徳的に正しいものとはインパクトだけでなく、
意図を加味して判断されるべきものと考えられます。例)戦争反対を訴えるために写真や動画を使って伝える行為は、
悲惨な光景でインパクトが大きくても、それ自体が否定されるべきものではない、など。 - パラソーシャルな関係が持つ影響力、エコーチャンバー、フィルターバブルの影響を意識する
4-2. メディア出演や出版物での言及
- メディアを通じた医療情報は影響力が大きいため、科学的根拠に基づいた内容かつ偏りのない表現を心がける必要があります。
- 特に精神疾患や精神医療に関する報道や番組は、センセーショナルな内容で視聴者の興味を引きがちですが、
偏見を生む表現は厳に慎むべきです。 - 公共の場で特定の患者を例示する場合は、必ず匿名化や仮名化を行い、
本人や関係者の承諾を得ることが必須です。
5. 学会や専門団体によるチェック体制とガバナンス
- 日本精神神経学会や各都道府県の医師会などは、会員に対する倫理指導や研修プログラムを実施しています。
- 不適切な情報発信が行われた場合、学会が注意喚起や処分に踏み切るケースもあり、
専門家としての責任を常に自覚する必要があります。 - 大学や研究機関、病院内の倫理委員会も重要な役割を果たしており、
情報発信にあたって疑義がある場合は相談することが推奨されます。
6. まとめ
- 基本的な医療倫理原則(自律尊重・善行・無害・正義)
に基づき、正確かつ適切で公平な情報を提供する。 - 日本精神神経学会の倫理指針をはじめ、各種ガイドラインを熟読し、
専門家として責任ある情報発信を行う。 - 患者のプライバシー・尊厳の保護を最優先し、
個人情報保護法や守秘義務の遵守を徹底する。 - メディアやSNS上では誤解を招かない表現に努め、
偏見を助長しないよう注意する。 - 学会や倫理委員会等のガバナンスを活用し、
発信前に疑義があれば相談する。
精神医学領域における医療情報発信は、患者や一般社会の理解を深め、
偏見や差別を減らすためにも非常に重要な役割を担っています。一方で、誤った情報や表現が与える影響も大きいため、
医療者は倫理規定を踏まえた慎重な対応が求められます。これらの倫理的原則・指針を遵守することで、
精神医学に携わる専門家として質の高い医療と社会貢献を実現することが期待されます。
刑法、民法に関係するもの
精神医学領域での医療情報発信においては、医療倫理や学会のガイドラインだけでなく、
刑法(秘密漏示罪や名誉毀損など)や民法(不法行為責任など)に関わる可能性があります。
以下で主なポイントを整理します。
1. 刑法との関係
1-1. 秘密漏示罪(刑法第134条)
- 概要
医師・歯科医師・薬剤師・助産師などが、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合に成立する犯罪で、
刑法第134条で規定されています。 - 精神科医療での注意点
- 患者の病名や症状、家族構成、治療状況など、プライバシー性の高い情報を、
守秘義務に反して漏らす行為が該当し得ます。 - 学会発表や論文、SNS等での情報発信に際し、個人が特定されうる形で症例を紹介すると、
秘密漏示罪に該当する可能性があります。 - 「本人の同意があれば良いのでは?」と考えられることもありますが、
同意を得ているか・情報開示の範囲が明確かなど、慎重な確認が必要です。
- 患者の病名や症状、家族構成、治療状況など、プライバシー性の高い情報を、
1-2. 名誉毀損罪や侮辱罪(刑法第230条など)
- 概要
他人の名誉を害する情報を公表した場合、名誉毀損罪(230条)、公然と人を侮辱する場合は
侮辱罪(231条)に問われる可能性があります。 - 精神科医療での注意点
- 患者の病状などを不適切に表現することで、その人の社会的評価が低下するような状況を
作り出した場合、名誉毀損が成立し得ます。 - 病名や診断が正確であっても、それを公表する必要性や公表方法によっては
名誉毀損に該当する可能性があります。
- 患者の病状などを不適切に表現することで、その人の社会的評価が低下するような状況を
2. 民法との関係
2-1. 不法行為責任(民法第709条など)
- 概要
故意または過失により他人に損害を与えた場合、加害者は損害賠償責任を負います。 - 精神科医療での注意点
- 患者の個人情報を不注意(過失)で漏洩した場合、精神的苦痛や社会的損害を被ったとして
患者から損害賠償請求を受ける可能性があります。 - SNSでうっかり個人が特定できる情報を掲載してしまった、講演会の資料に患者のプライベートが
分かる情報を載せた、といったケースが代表例です。
- 患者の個人情報を不注意(過失)で漏洩した場合、精神的苦痛や社会的損害を被ったとして
2-2. プライバシー権の侵害・パブリシティ権の侵害
- 概要
日本の民法や判例上、プライバシー権や肖像権などの人格権が保護されており、
それらを侵害することで慰謝料等の損害賠償責任が認められる場合があります。 - 精神科医療での注意点
- 患者が特定される形での病状開示は、プライバシー権の侵害にあたる恐れがあります。
- 著名人や芸能人の場合、その人のイメージや商品価値(パブリシティ権)を毀損する
情報発信を行うと、追加的な損害賠償請求に発展することもあります。
3. 実務上の留意点
- 守秘義務の徹底
- 刑法上の秘密漏示罪や医師法上の守秘義務違反となるリスクを避けるため、
発信内容を慎重にチェックする。 - 症例紹介の際は個人が特定されないよう匿名化・加工を行い、可能な限り本人の同意を得る。
- 刑法上の秘密漏示罪や医師法上の守秘義務違反となるリスクを避けるため、
- 情報発信の目的と必要性の検討
- 医療情報発信の目的(教育的意義、社会啓発の意義など)が正当であるか、
また患者の権利を不必要に侵害しないかを吟味する。 - 必要以上にセンセーショナルな表現やプライベートな情報に踏み込まない。
- 医療情報発信の目的(教育的意義、社会啓発の意義など)が正当であるか、
- 正確性と根拠の提示
- 精神医学領域の情報はデリケートであるため、正確性を確保するとともに、
根拠を明示することが望ましい。 - 不十分なデータや一部の結果のみを過度に強調すると、誤解や不安を招き、
のちに法的トラブルへ発展する可能性がある。
- 精神医学領域の情報はデリケートであるため、正確性を確保するとともに、
- 専門家としての責任とリスク管理
- 医療従事者としての肩書きで情報を発信する場合、その信頼性から社会的影響は
大きいことを自覚する。 - 学会や倫理委員会、病院の法務部門などに事前相談することで、
刑事・民事トラブルのリスクを低減できる。
- 医療従事者としての肩書きで情報を発信する場合、その信頼性から社会的影響は
4. まとめ
- 刑法上は、医療従事者の守秘義務違反として「秘密漏示罪」(刑法第134条)が代表的で、
名誉毀損や侮辱罪に該当するケースもあり得ます。 - 民法上は、不法行為責任(709条)による損害賠償請求やプライバシー権侵害、
名誉毀損による慰謝料請求などのリスクが考えられます。 - 特に精神医学分野では患者情報がセンシティブであり、情報発信の際は患者のプライバシー・名誉への
影響を常に考慮し、慎重な配慮が不可欠です。 - 発信する前に法的・倫理的な問題がないか十分にチェックし、必要に応じて専門家や
病院内の倫理委員会・法務部門に相談することが望まれます。
こうした留意点を守りながら情報を発信することで、刑事・民事トラブルを回避しつつ、
精神医学の正しい理解と適切な医療啓発に繋げることが期待されます。
ゴールドウォータールール
ゴールドウォータールール(Goldwater Rule)とは、アメリカ精神医学会(APA)が定めた倫理規定の一つで、
精神科医が公の場で、直接診察を行っていない人物(特に公人)について、専門家としての診断や意見表明をしない
ように求めるものです。以下では、このルールが生まれた経緯や内容、その背景となった問題点を解説します。
1. ゴールドウォータールールの成立経緯
1-1. 1964年アメリカ大統領選挙と「Fact」誌事件
- バリー・ゴールドウォーター(Barry Goldwater)は、1964年の米大統領選挙における共和党候補でした。
- 雑誌「Fact」誌が複数の精神科医を対象に「ゴールドウォーター氏は大統領として精神的に適格か」
についてアンケート調査を実施し、診療していないにもかかわらず「不適格」「精神的に問題がある」などと回答を公表。 - ゴールドウォーター氏は名誉毀損で提訴し勝訴。これが“遠隔診断”が名誉や権利を著しく侵害し得るという
教訓を残しました。
1-2. APAによる倫理規定の制定
- この事件を受け、アメリカ精神医学会(APA)は1973年に「診察していない個人の精神状態を公に評価・診断してはならない」
という倫理規定を策定。後に「ゴールドウォータールール」と呼ばれるようになりました。 - 現在では「Principles of Medical Ethics: with Annotations Especially Applicable to Psychiatry」第7条(7.3節)に
明記されています。
2. ゴールドウォータールールの主旨と内容
- 直接診療を行っていない人物について診断を行わない
- 医師と患者の信頼関係がない状況での言及を避ける
- 公共の利益を損なう可能性
- 専門家としての信用毀損と法的リスク
3. 現代におけるゴールドウォータールールの意義と議論
3-1. メディア環境の変化
- SNSやオンラインメディアを通じて、政治家や著名人に関する情報が瞬時に広まり、
精神科医による「専門家見解」の発言が大きな社会的影響を持つ。
3-2. 公人への言及に対する葛藤
- 「公職者の精神状態を指摘すべき」という公共の利益・表現の自由との兼ね合いと、
倫理規定をどこまで厳格に適用するかが議論に。 - 特にトランプ大統領の言動をめぐり、ゴールドウォータールールが再度注目されました。
3-3. 例外や解釈の幅
- 「公人の行動を一般論として分析・解説」までは許容されるが、
診断名の断定は避けるべきだとAPAは強調。
4. ゴールドウォータールールが示唆する点
- 精神医学の信頼性維持
- 個人の名誉やプライバシー保護
- 表現の自由と専門家倫理のバランス
5. 日本におけるゴールドウォータールールの認識
- 日本精神神経学会に同名ルールはないが、診察していない人物の病名を断定的に述べるのは
倫理・名誉毀損の観点でも問題がある。 - 日本でも「有名人の言動を精神科医が解説」する機会はあるが、
診断名の具体的言及には慎重が求められる。
まとめ
- ゴールドウォータールールは、1964年のバリー・ゴールドウォーター氏への
“遠隔診断”騒動を受けて定められた、
「直接診察を行っていない公人について医学的診断・評価を公に述べない」
というAPAの倫理規範。 - 公人であっても名誉やプライバシーは守られるべきであり、
精神科医の専門的見解が社会に及ぼす影響は非常に大きい。 - 日本には同名の規定はないが、同様の配慮が学会倫理指針で求められており、
診療していない人物の精神状態を断定的に語らない
ことは専門家として不可欠な姿勢とされる。
インパクトと意図について
道徳心理学において、人の行為を評価するうえで大きな論点となるのが
「インパクト(影響・結果)」と「意図(動機)」です。同じ行為でも、
そこに至る動機や結果の大小によって、人々の評価は変化します。以下では、
それぞれの概念と道徳判断における扱われ方を解説します。
1. インパクト(影響・結果)の視点
(1) 行為の結果や影響に注目する見方
- 結果主義・功利主義:
行為がもたらす「最大多数の最大幸福」の大きさによって評価を下す。 - 道徳心理学:
どれくらい多くの人に利益をもたらしたか、害を与えたかなどが
道徳評価に影響することが研究で示されている。
(2) 道徳的評価と「予測可能性」や「回避可能性」
- どれほど結果を予測できたか、回避できる余地があったかによって
行為者の責任の重さや評価が変わる。
2. 意図(動機・目的)の視点
(1) 行為者の心理的状態に注目する見方
- 意図主義:
行為の動機や目的が最も重要と考える立場。カント倫理学が代表例。
(2) 道徳心理学での研究例
- 結果が良くても利己的意図であれば評価は下がり、結果が悪くても善意が明確だと
許容される場合があるなど、意図の違いによって評価が大きく変わる。
3. インパクトと意図の交互作用
(1) 多くの道徳判断は「折衷的」
インパクト(結果)と意図(動機)の両面を総合的に見て評価することが多い。
(2) 責任帰属のプロセス
- 結果責任:結果が深刻だと非難が強まる。
- 意図責任:悪意や故意が強ければ非難が強まり、善意なら非難が弱まる。
(3) 「モラル・ラック(moral luck)」の問題
- 良い意図でも不運で結果が悪化した、悪い意図でも結果が軽微だったといった場合に
どう責任を帰属するかは倫理学・道徳心理学の大きな論争となっている。
4. まとめ
- インパクト(影響・結果):功利主義や結果主義が代表的。
行為がもたらす利益・害の大きさを重視。 - 意図(動機・目的):カント倫理学などが代表的。
行為に至る動機や意志を重視。 - 現実の道徳判断:多くは両者を総合的に考慮する。
結果の大小や意図の善悪、運の要素などが複雑に絡み合う。
日本における医師や医療機関の広告などを規律する法律として、主に以下の2つが重要です。
-
医師法、医療法(いわゆる医療広告規制を含む)
一般的に「医療広告規制法」と呼ばれることがありますが、実際には「医療法」の中で医療広告に関する規定が定められています。本回答では、医師法の概要と医療広告を中心とした医療法の概要について解説します。
1. 医師法とは
医師法(昭和23年法律第201号)は、医師の免許や業務範囲、義務、罰則などを定める法律です。具体的には以下のような規定が含まれます。
- 免許と登録
- 医師として業務を行うには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。
- 医師名簿に登録された後でなければ、医師を名乗ることはできません。
- 業務に関する義務
- 無診察治療の禁止: 診察をせずに治療行為を行うことは原則として禁止されています。
- 異状死体の届出義務: 死体や出産後の母体に異常があると判断した場合には、警察等への届出が義務付けられています。
- 診療録(カルテ)の記載義務: 患者の診療内容を記録し保存することが求められています。
- 守秘義務
- 医師は正当な事由なく、診療上知り得た患者の秘密を漏らしてはならないとされています。
- 懲戒・罰則
- 法律違反があった場合には免許の取消し・停止等の行政処分や罰則が科される場合があります。
医師法は、「国民が安心して医療を受けられるようにする」「適切な医療行為が行われるようにする」ための基本的な枠組みを定める法律です。医師免許の取得・管理や業務上の責任などに関する重要な規定が多く含まれます。
2. 医療広告(医療法)について
医師法とあわせて、医療機関や医療サービスに関する広告規制を定めているのは、主に「医療法」です。医療法(昭和23年法律第205号)は、医療提供体制全般を定めている総合的な法律ですが、その中に医療広告に関する規定があります。ここでは、一般的に「医療広告規制法」と呼ばれることもある、医療広告規制のポイントを解説します。
2-1. 医療法における医療広告の規制概要
- 広告可能な事項の限定
医療広告では、以下に該当する事項のみ広告できることが原則です。- 広告する医療機関の基本情報(名称・住所・電話番号・診療科目など)
- 厚生労働省令で定める客観的な実績、治療内容、医療機器に関する情報 など
- 公的な認定、許可を受けている場合はその事実
- 虚偽広告や誇大広告の禁止
- 医療法第6条の5などで、虚偽や誇大な表現の広告を禁止しています。
- 治療の有効性や安全性を実際以上にうたったり、患者を誤認させるような表現は違反となります。
- 比較広告や体験談の扱い
- 比較広告は、科学的根拠が明確でないと誤認を招く恐れがあるため、厳しく規制されています。
- 患者個人の体験談に関しても、事実の裏付けが十分でないものを広告に用いることは認められません。
- ウェブサイトやSNSでの表現
- インターネットでの情報発信も広告とみなされる場合があります。その場合は医療広告規制の対象となるため、広告可能事項以外の内容を過度にPRすることは禁じられています。
- 「広告」に該当するかどうかは、表示場所や目的、一般人が閲覧可能かどうか、誘引性(受診を誘うか)などによって総合的に判断されます。
- 根拠のある情報提供の重要性
- 医療に関する情報は、患者にとって非常に重要である一方、誇大広告や不正確な表現によって不利益を被るおそれも大きいです。
- そのため、広告する際には、エビデンス(科学的根拠)に基づいた情報であることを明確に示す必要があります。
2-2. 違反時の罰則・対応
医療広告規制に違反した場合、厚生労働大臣や都道府県知事等が指導・勧告・命令を出すことができます。命令に従わない場合や違反が悪質な場合、罰金などの行政処分が科されることがあります。また、医師個人に対しては医師法上の懲戒処分が検討される場合もあります。
3. まとめ
- 医師法
- 医師の免許・業務・守秘義務などを定める基本的な法律。
- 無診察治療の禁止や懲戒など、医師としての活動全体にわたる義務や責任を規定している。
- 医療法(医療広告規制)
- 医療提供体制全般を定める法律であり、医療広告に関する規制も含む。
- 広告できる事項や、虚偽・誇大広告の禁止を定め、患者が正しい情報を得られるようにすることを目的としている。
- 違反すると行政処分や罰則の可能性がある。
このように、医師法は医師個人の資格や業務上の義務を中心に規定し、医療法(医療広告規制を含む)は医療機関や医療サービスに関する広告・運営体制などを規定しています。医師が適切に業務を行い、患者が安心して医療を受けられる体制を整えるために、両方の法律が重要な役割を果たしているといえます。
情報発信者の心的疲労について
精神科医YouTuberとして時事問題を語ることは、一般的な情報発信とは異なる精神的負担を伴います。以下に、その主な負担と対策について解説します。
1. 炎上リスクと批判への耐性
- 負担: 社会的にセンシティブなテーマを扱うことで、反対意見や批判を受ける可能性が高まる。特に政治・社会問題に関する発言は、意図しなくても特定の層から反感を買うことがある。
- 対策:
- 事前にリスクを想定し、言葉選びを慎重に行う。
- 「医学的見解」「個人の意見」といった枠組みを明確にし、発言の意図を誤解されにくくする。
- SNSのコメントやDMをすべてチェックしないようにし、必要以上にストレスを受けない仕組みを作る。
2. 感情的な影響
- 負担: 社会問題の背景には悲劇的な事件や深刻な人権問題が含まれることが多く、それを繰り返し目にすることで共感疲労(エンパス疲れ)が起こりやすい。
- 対策:
- 一定の距離感を保つ。「ジャーナリスト」ではなく「精神科医としての立場」で解説することを意識する。
- 情報収集の時間を制限し、仕事とプライベートの境界を明確にする。
- できるだけポジティブな側面や解決策を提示し、視聴者と共に前向きな視点を持てるようにする。
3. 専門家としての責任
- 負担: 精神科医として語る以上、不確実な情報を提供すると信用を損なうリスクがある。また、発言が社会的な影響を持ちやすい。
- 対策:
- できるだけエビデンスに基づいた内容を発信し、感情論に流されないようにする。
- 「あくまで現時点の知見ではこう考えられる」といった表現を用い、断定を避ける。
- 内容に迷ったときは、無理に発信せずに様子を見る。
4. 視聴者および身近な人らとの関係性の変化
- 負担: 時事問題に言及すると、視聴者が「政治的立場」や「社会的スタンス」を勝手に推測し、それによってファン層が変化する可能性がある。また身近な人らとも対立したり、誤解されるリスクがある。
- 対策:
- あくまで「精神医学的な視点を提供する」という立ち位置を貫く。
- 価値観の押し付けにならないよう、幅広い視点を紹介する。
- 必要以上に視聴者の反応を気にせず、「長期的な信頼関係を築く」ことを意識する。
- アンチはすぐ出てくるパターンもあれば、もともとファンだった人が長い時間をかけてアンチになることもある
5. 情報の流動性によるストレス
- 負担: 時事問題は刻一刻と変化し、短期間で意見が変わることもある。過去の発言と最新の状況が食い違うことに対するプレッシャーが生じる。
- 対策:
- 「時点情報である」ことを明確にし、常にアップデートする姿勢を示す。
- 以前の発言と変わった場合は「新しい情報が出たため見解を更新する」と説明し、柔軟性を持たせる。
- すべての時事問題を追いかけようとせず、扱うテーマを絞る。
6. 動画制作の心理的負担
- 負担: センシティブな話題を取り扱う際には、話し方や構成に細心の注意を払う必要があり、通常の動画よりも制作のストレスが大きくなる。
- 対策:
- 台本を作成し、言葉遣いを事前にチェックする。
- 編集時に第三者のチェックを入れ、問題がないか確認する。
- 時には「軽めの話題」を間に挟み、精神的なバランスを取る。
まとめ
精神科医YouTuberとして時事問題を語ることには、大きな影響力がある反面、精神的負担も無視できません。しかし、適切な対策を講じることで負担を軽減しつつ、社会に貢献することが可能です。
- 炎上リスクを想定し、発言の枠組みを明確にする
- 感情的に飲み込まれないよう、適度な距離感を保つ
- 専門家としての信頼性を維持し、感情論に流されない
- 視聴者との関係を長期的視点で築く
- 情報の流動性に柔軟に対応する
- 動画制作の負担を分散する
これらのポイントを意識することで、時事問題を語る際の精神的負担を減らしながら、影響力を最大限に活かすことができるでしょう。
注意:
これらの文章はAIを用いて作成し、益田裕介本人の目で確認、修正されています。
参考)WELQの問題で改めて考える、信頼できるネットの医療情報とは? 朽木誠一郎さんに聞く
https://www.huffingtonpost.jp/2016/12/08/welq-kuchiki-seiichiro_n_13510758.html